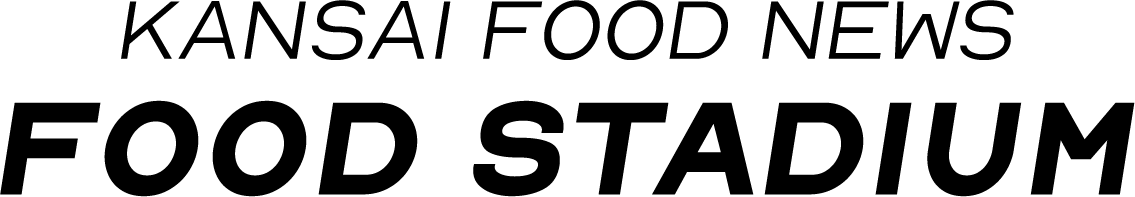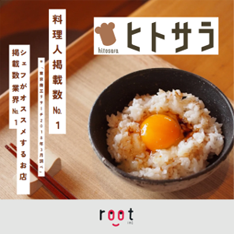京都を中心に多彩な業態を展開するMASTERMIND(京都市下京区)。和食からイタリアンに大衆酒場、ギョウザ専門店から韓国焼肉までコンセプトは様々。「マーケットが求めるものに合わせるより、僕らの『食べてほしい!』という熱意を提供するのが得意な会社なんです」と話すのは、代表の金井哲郎氏。コロナ禍では東京進出も果たし、現在は冷凍食品工場を開設し新事業にも取り組み、労働環境の向上を目指す。創業から22年、MASTERMINDの現在地について、金井氏に話を聞いた。

MASTERMIND代表取締役:金井哲郎氏
兵庫県生まれ。25歳から飲食業に従事し、サービスの仕事に魅了される。2003年、京都に「ごはんや蜃気楼」をオープンし独立。その後、京都で「Ristorante美郷」、「DINING+CAFE&BAR閏(うるう)」、「Cucina Italiana東洞」、「酒場たいげん」、「Brisket RONY(ブリスケ ロニー)」、「ぎょうざ処 亮昌(すけまさ)」など京都で多彩な業態を展開。2021年には東京・大手町に「taverna ハル」をオープンし東京進出も果たす。
MASTERMIND(HP):https://mrmd.co.jp/
枚方の撤退を経て改めて実感したプロダクトアウトの店づくり
―京都を中心に様々な業態を展開されていますが、出店の方針はありますか?
金井氏:その時でやりたいことをやっている感じです。ジャンルも和食からイタリアン、ギョウザまで幅広く、単価もしっかりしたレストランから大衆酒場まで様々。「ぎょうざ処 亮昌」のみ店舗展開しており、京都市内に3店舗あります。京都を主戦場としているので、同じ街に同じ業態はそんなに必要ないかと思いますし、何よりは、人との出会いを大事にしてきました。その結果、様々な業態になっています。マーケットが求めるものを探って店を作っているというよりも、最初に「この人と働きたい」や「この料理を食べてほしい」という思いから店を作っています。
―マーケットインよりプロダクトアウトな店づくりが御社の特徴ですね。
金井氏:それは強く実感していることですね。以前、2011年に大阪・枚方で100席規模のイタリアンを出店したことがありました。今まで「これを食べてほしい!」という思いから店を作ってきた僕らですが、そこはエリア特性に合わせに行った店づくりをしました。枚方はファミリー層が多く、若い頃は都会でしゃれたイタリアンに親しんでいた人が、家族を持って住んでいる人が多いとイメージしました。パスタも、スパゲッティやタリアテッレ、フジッリなどのセミドライパスタを製造する本格的なイタリアンを出していましたが、それがなかなか伝わらなかったですね。結果として撤退することになりました。その経験からも、やはり自分達のアイデンティティは「これを食べてほしい!」という思いを起点にした店づくりなんだなと実感しました。

韓国のソウルフード「チャドルバギ」専門店「Brisket RONY」が好調
―現在、特に好調な店舗は?
金井氏:京都・四条の「Brisket RONY」ですね。韓国式焼肉のチャドルバギの専門店です。2019年8月にオープンしてすぐにコロナ禍になってしまったので最初はどうしようかと思いましたが、オープン時は物珍しさからメディア取材が相次ぎ、さらにそこから口コミが広がって昨対1.5倍ほどで売上が伸びています。

―「チャドルバギ」とは?
金井氏:韓国式の焼肉で、極薄切りにしてくるっと筒状になったブリスケを、プロトン凍結という技術で冷凍して保形し、それをジンギスカン鍋で焼く焼肉です。鍋の油溜まりの部分には出汁卵を注ぎ、肉とともに楽しみます。日本ではあまりなじみがなく、韓国ではサムギョプサルの方が有名ですが、現地ではサムギョプサル以上に親しまれている料理なんです。以前、韓国の友人にチャドルバギの店に連れて行ってもらい、感動したのがきっかけです。やはり「これを食べてほしい!」という思いが起点ですね。「Brisket RONY」では、チャドルバギを自分たちなりにアレンジ。黒毛和牛のブリスケを使用し、特製の甘酸っぱいタレを用意。一品料理も充実させ、お酒とともに楽しめる店です。
冷凍食品工場で働き方改革、新しい商売のかたちを模索
―現在、特に力を入れていることは?
金井氏:2023年12月に120坪ほどの食品工場をつくりまして、最近はそこにつきっきりな感じです。当社の「ぎょうざ処 亮昌」の生ギョウザの製造をはじめ、各店の仕込みの一部や、OEMで外部の飲食店に卸す冷凍食品の製造などを行っています。
―その狙いは?
金井氏:ひとつは、労働環境の向上です。うちはチェーン店でなく、各店に料理長がいて各々の個性を発揮した料理を提供している。その下にいるスタッフ全員が料理長と同じように働けるかというと、そうとは限らない。やはり昔と今の世代では考え方も変わってきているのを感じています。昔は料理長になりたい、独立したい、など仕事に重きを置く人も多かったですが、最近は仕事と私生活のバランスを大事にする人も多い。料理長クラスに上り詰めなくても、長く働ける環境を整えたいという思いがあります。例えば年を取って現場でバリバリ動けなくなっても、工場での勤務があれば働き続けられる。工場と言っても、うちは機械で大量生産するのではなく職人が手作りしています。技術を持った人間が現場のようなハードな環境でなく能力を発揮できます。仕込みをまとめて行えば、各店舗の負担軽減にもつながります。

―工場を開設していかがですか?
金井氏:冷凍機器も導入しているのですが、現在の冷凍技術は驚くほど進歩していて、うまく作れば店舗でつくるものと遜色ない味わいが再現できる。ただ店舗で製造するものとは勝手が違い、工場で製造する食品ならではの調理法や原材料などを勉強しましたね。例えば、冷凍シュウマイを開発し、現在の卸先は10軒ほど。「レシピがお金になる」状況が作れたらと思っています。飲食店としての売上以外にも収益を上げていきたい。そして製造の次にぶち当たるのが物流の問題。つくったものを卸先に配送するにも簡単ではない。新しい事業なので一つ一つ、手探りでクリアしている状況です。
―今後の展開は?
金井氏:工場の事業をうまく回しつつ、チャンスがあれば京都を中心に、その時にやりたい業態を人との出会いでできれば。また、うちの会社では社員と素材の産地巡りも頻繁に行っています。最近だと三重の伊賀牛の産地に行ったり。食材って一つ一つに歴史やストーリーがある。学生時代は歴史学を専攻していたので、食の歴史にロマンを感じるんです。今年で創業から22年、何度もピンチを乗り越えてきましたが、これからもそういうロマンを大事にしながら飲食店をやれたらと思っています。
―一つ一つ思いを持って店づくりをするMASTERMIND。新事業にも取り組み、今後の展開も楽しみですね。本日はありがとうございました!